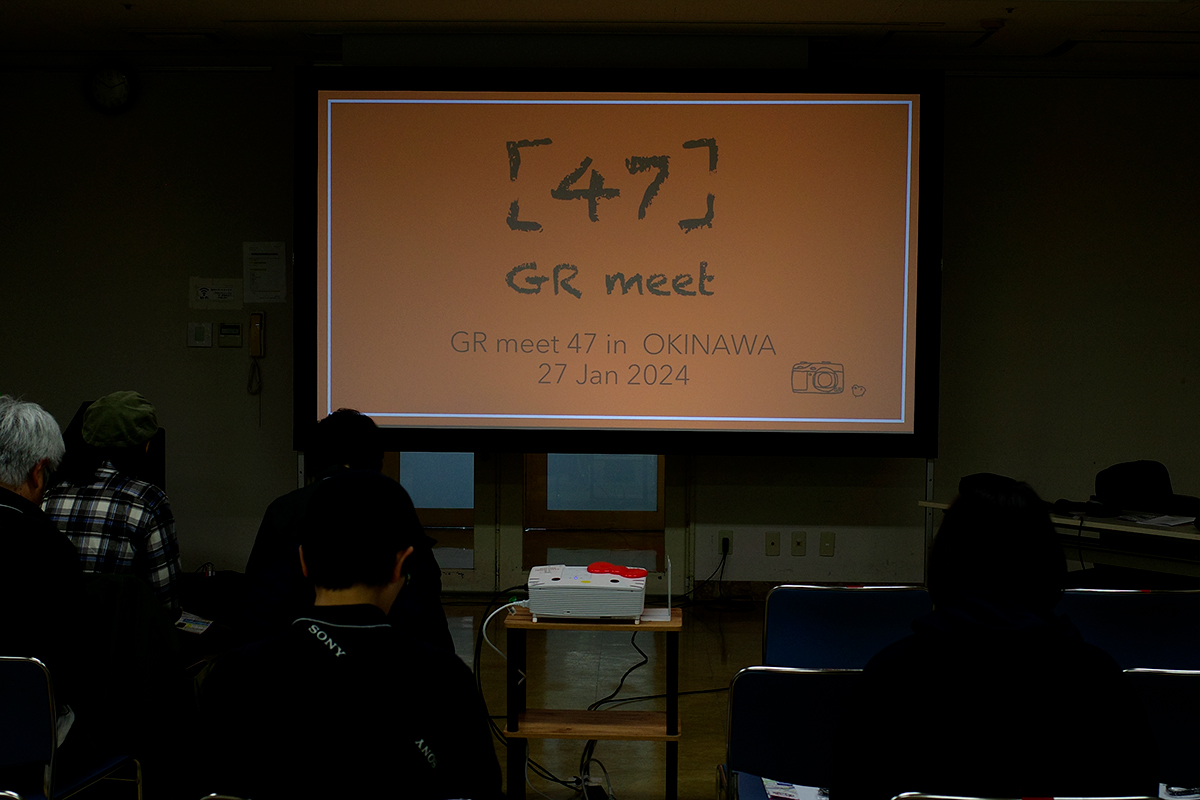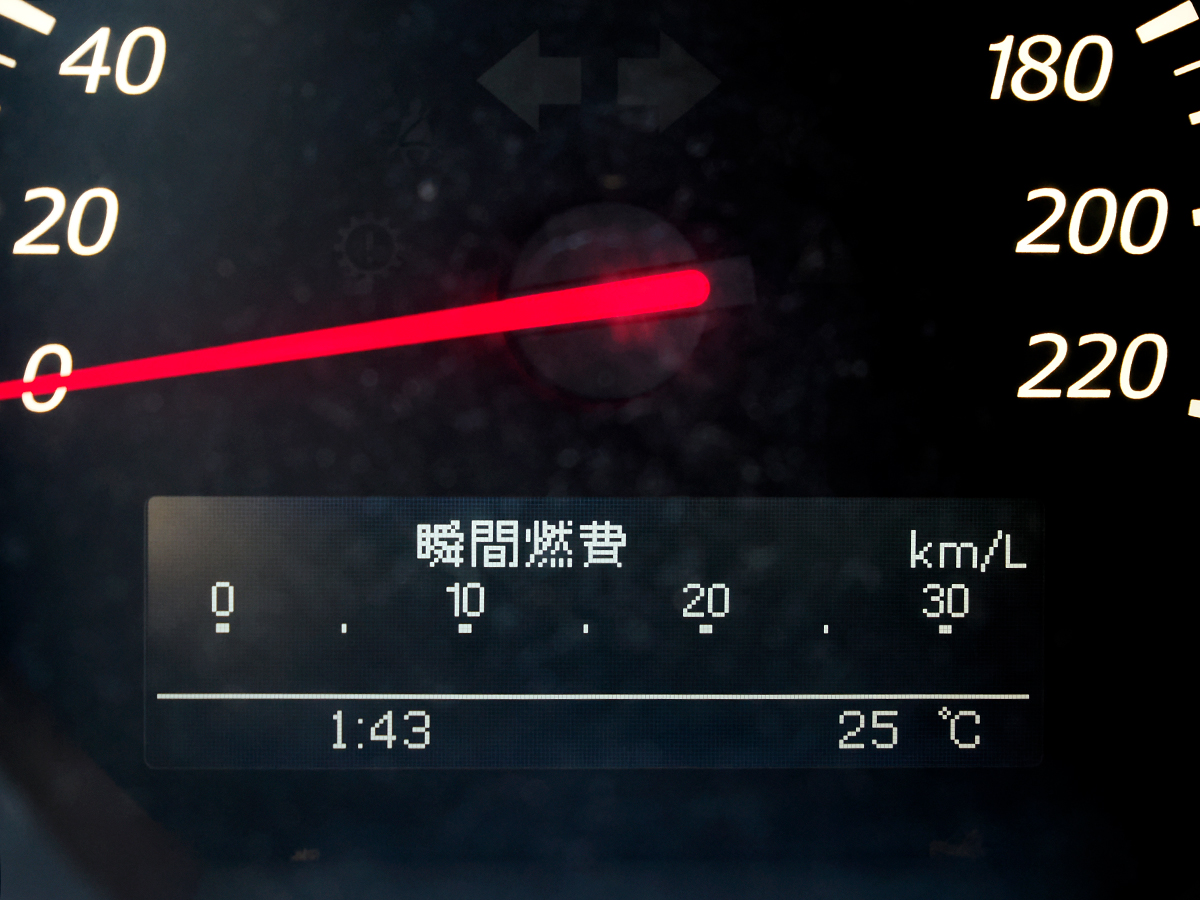|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生まれてから19年間過ごした東京ですが、どうも都会の生活は苦手で落ち着かないものでした。そして、その東京よりも長くなった沖縄での生活が続いています。
しかし、長いからといって、その土地の人になることは出来ません。こうしてみると、本当に自分自身の落ち着ける居場所は何処にもないような、そんな気もしてきます。
でも、これからも沖縄に住み、あちらの島やこちらの島を転々としながら、野生動物たちの撮影を続けていくことに変わりはないでしょう。
その仕事にしても決して要領のよいものでなく、いつもどこかワンテンポずれたことばかりのように感じます。
ゆったりと流れていく時の中に浮かぶ、南の島での毎日を少しずつ紹介できればと思います。
しかし元来が怠け者で、夏休みの絵日記もまともに付けたことのない性格、どれくらいのペースで更新できるかは、当の本人にも全くわかりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<トップページ
謹賀新年 本年もよろしくお願い致します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各種お問い合わせは、こちらまでお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<トップページ
管理者ログイン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バックナンバー |2001年| 11月| 12月| |2002年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2003年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2004年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2005年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2006年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2007年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2008年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2009年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2010年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2011年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2012年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2013年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2014年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2015年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2016年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2017年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2018年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2019年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2020年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2021年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2022年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2023年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2024年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| 8月| 9月| 10月| 11月| 12月| |2025年| 1月| 2月| 3月| 4月| 5月| 6月| 7月| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||